 |2017-12-01|運慶の後継者たち―康円と善派を中心に|東京国立博物館・本館14室|
◈◈ 開催期間は 2017-08-29→12-03 です。
「運慶展」と同時期で、こちらも観てきました。
|2017-12-01|運慶の後継者たち―康円と善派を中心に|東京国立博物館・本館14室|
◈◈ 開催期間は 2017-08-29→12-03 です。
「運慶展」と同時期で、こちらも観てきました。

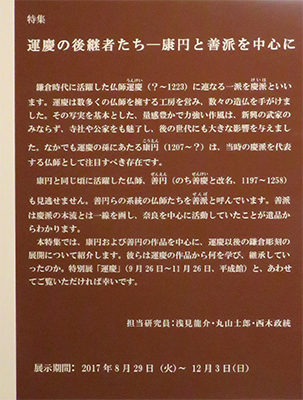 読みづらいので書き起こします。
特集
鎌倉時代に活躍した仏師運慶(?〜1223)に連なる一派を慶派といいます。
運慶は数多くの仏師を擁する工房を営み、数々の造仏を手がけました。
その写実を基本とした、量感豊かで力強い作風は、新興の武家のみならず、
寺社や公家をも魅了し、後の世代にも大きな影響を与えました。
なかでも運慶の孫にあたる康円(こうえん)(1207〜?)は、当時の慶派
を代表する仏師として注目すべき存在です。
康円と同じ頃に活躍した仏師、善円(ぜんえん)(のち善慶と改名、1197
〜1258)も見逃せません。善円らの系統の仏師たちを善派と呼んでいます。
善派は慶派の本流とは一線を画し、奈良を中心に活動していたことが遺品
からわかります。
本特集では、康円および善円の作品を中心に、運慶以後の鎌倉彫刻の展開
について紹介します。彼らは運慶の作品から何を学び、継承していったのか。
特別展「運慶」(9月28日〜11月26日、平成館)と、あわせてご覧いただけ
れば幸いです。
◈◈作品リスト(公式サイトより)
文殊菩薩立像 鎌倉時代・13世紀 C-23
重文 愛染明王坐像 康円作 鎌倉時代・文永12年(1275)京都・神護寺蔵
重文 東方天眷属立像(四天王眷属のうち)
康円作 鎌倉時代・文永4年(1267) C-1834-1
重文 南方天眷属立像(四天王眷属のうち)
康円作 鎌倉時代・文永4年(1267) C-1834-2
重文 地蔵菩薩立像 善円作 鎌倉時代・延応2年(1240)奈良・薬師寺蔵
地蔵菩薩立像 鎌倉時代・13世紀 C-332
重文 菩薩立像 鎌倉時代・13世紀 C-20
重文 文殊菩薩坐像(文殊菩薩騎獅像および侍者立像のうち) 興福寺伝来
康円作 鎌倉時代・文永10年(1273) C-1854-1
重文 獅子像(文殊菩薩騎獅像および侍者立像のうち) 興福寺伝来
康円作 鎌倉時代・文永10年(1273) C-1854-6
重文 光背および蓮華座(文殊菩薩騎獅像および侍者立像のうち)興福寺伝来
康円作 鎌倉時代・文永10年(1273) C-1854-7
重文 仏陀波利三蔵立像(文殊菩薩騎獅像および侍者立像のうち)興福寺伝来
康円作 鎌倉時代・文永10年(1273) C-1854-5
重文 善財童子立像(文殊菩薩騎獅像および侍者立像のうち) 興福寺伝来
康円作 鎌倉時代・文永10年(1273) C-1854-3
重文 ★于てん王立像(文殊菩薩騎獅像および侍者立像のうち) 興福寺伝来
康円作 鎌倉時代・文永10年(1273) C-1854-2
重文 大聖老人立像(文殊菩薩騎獅像および侍者立像のうち) 興福寺伝来
康円作 鎌倉時代・文永10年(1273)) C-1854-4
★てん=門がまえに眞
フラッシュ禁止、撮影可(ないものは撮影不可)でした。
文殊菩薩立像
読みづらいので書き起こします。
特集
鎌倉時代に活躍した仏師運慶(?〜1223)に連なる一派を慶派といいます。
運慶は数多くの仏師を擁する工房を営み、数々の造仏を手がけました。
その写実を基本とした、量感豊かで力強い作風は、新興の武家のみならず、
寺社や公家をも魅了し、後の世代にも大きな影響を与えました。
なかでも運慶の孫にあたる康円(こうえん)(1207〜?)は、当時の慶派
を代表する仏師として注目すべき存在です。
康円と同じ頃に活躍した仏師、善円(ぜんえん)(のち善慶と改名、1197
〜1258)も見逃せません。善円らの系統の仏師たちを善派と呼んでいます。
善派は慶派の本流とは一線を画し、奈良を中心に活動していたことが遺品
からわかります。
本特集では、康円および善円の作品を中心に、運慶以後の鎌倉彫刻の展開
について紹介します。彼らは運慶の作品から何を学び、継承していったのか。
特別展「運慶」(9月28日〜11月26日、平成館)と、あわせてご覧いただけ
れば幸いです。
◈◈作品リスト(公式サイトより)
文殊菩薩立像 鎌倉時代・13世紀 C-23
重文 愛染明王坐像 康円作 鎌倉時代・文永12年(1275)京都・神護寺蔵
重文 東方天眷属立像(四天王眷属のうち)
康円作 鎌倉時代・文永4年(1267) C-1834-1
重文 南方天眷属立像(四天王眷属のうち)
康円作 鎌倉時代・文永4年(1267) C-1834-2
重文 地蔵菩薩立像 善円作 鎌倉時代・延応2年(1240)奈良・薬師寺蔵
地蔵菩薩立像 鎌倉時代・13世紀 C-332
重文 菩薩立像 鎌倉時代・13世紀 C-20
重文 文殊菩薩坐像(文殊菩薩騎獅像および侍者立像のうち) 興福寺伝来
康円作 鎌倉時代・文永10年(1273) C-1854-1
重文 獅子像(文殊菩薩騎獅像および侍者立像のうち) 興福寺伝来
康円作 鎌倉時代・文永10年(1273) C-1854-6
重文 光背および蓮華座(文殊菩薩騎獅像および侍者立像のうち)興福寺伝来
康円作 鎌倉時代・文永10年(1273) C-1854-7
重文 仏陀波利三蔵立像(文殊菩薩騎獅像および侍者立像のうち)興福寺伝来
康円作 鎌倉時代・文永10年(1273) C-1854-5
重文 善財童子立像(文殊菩薩騎獅像および侍者立像のうち) 興福寺伝来
康円作 鎌倉時代・文永10年(1273) C-1854-3
重文 ★于てん王立像(文殊菩薩騎獅像および侍者立像のうち) 興福寺伝来
康円作 鎌倉時代・文永10年(1273) C-1854-2
重文 大聖老人立像(文殊菩薩騎獅像および侍者立像のうち) 興福寺伝来
康円作 鎌倉時代・文永10年(1273)) C-1854-4
★てん=門がまえに眞
フラッシュ禁止、撮影可(ないものは撮影不可)でした。
文殊菩薩立像
 東方天眷属立像、南方天眷属立像
東方天眷属立像、南方天眷属立像
 菩薩立像
菩薩立像

 文殊菩薩坐像
文殊菩薩坐像
 光背および蓮華座
光背および蓮華座
 獅子像
獅子像

 仏陀波利三蔵立像
仏陀波利三蔵立像
 善財童子立像
善財童子立像
 于てん王立像
于てん王立像
 大聖老人立像
大聖老人立像
 唯一善円作の地蔵菩薩、康円の愛染明王は撮影禁止でした…
↑検索してみましたが、慶派の影響を全く受けず、平安時代の作風そのままと
いう感じです。どちらがいいというより、好みですね。
愛染明王は最晩年の作らしく、見た途端に引きつけられる程、細部まで見事な
出来映えでした。頭の獅子?が可愛い(笑)
菩薩立像は作風が定慶風で綺麗ですが、ひねりが入っています。
康円の文殊菩薩は快慶のイメージとは全然違い、何だかしかめ面に見えました。
運慶は仏像を人間に近づけたけど、康円はほぼ人間みたいな距離感(親しみが
持てるという意味)です。
蓮華座の迦陵頻迦(かりょうびんが)は、片方が後補だそうです。
↓向かって左がオリジナル?(違ったりして(笑))
唯一善円作の地蔵菩薩、康円の愛染明王は撮影禁止でした…
↑検索してみましたが、慶派の影響を全く受けず、平安時代の作風そのままと
いう感じです。どちらがいいというより、好みですね。
愛染明王は最晩年の作らしく、見た途端に引きつけられる程、細部まで見事な
出来映えでした。頭の獅子?が可愛い(笑)
菩薩立像は作風が定慶風で綺麗ですが、ひねりが入っています。
康円の文殊菩薩は快慶のイメージとは全然違い、何だかしかめ面に見えました。
運慶は仏像を人間に近づけたけど、康円はほぼ人間みたいな距離感(親しみが
持てるという意味)です。
蓮華座の迦陵頻迦(かりょうびんが)は、片方が後補だそうです。
↓向かって左がオリジナル?(違ったりして(笑))
 康円の特徴はズバリ、目力ならぬへの字眉力とひねりなしの直立(笑)
ちょっと粗い彫りで硬い印象だったけど、愛染明王は素晴らしかったです。
運慶が見たら何と言ったかな…などと思いながら、会場を後にしました。
康円の特徴はズバリ、目力ならぬへの字眉力とひねりなしの直立(笑)
ちょっと粗い彫りで硬い印象だったけど、愛染明王は素晴らしかったです。
運慶が見たら何と言ったかな…などと思いながら、会場を後にしました。
|
 |2017-12-01|運慶の後継者たち―康円と善派を中心に|東京国立博物館・本館14室|
◈◈ 開催期間は 2017-08-29→12-03 です。
「運慶展」と同時期で、こちらも観てきました。
|2017-12-01|運慶の後継者たち―康円と善派を中心に|東京国立博物館・本館14室|
◈◈ 開催期間は 2017-08-29→12-03 です。
「運慶展」と同時期で、こちらも観てきました。

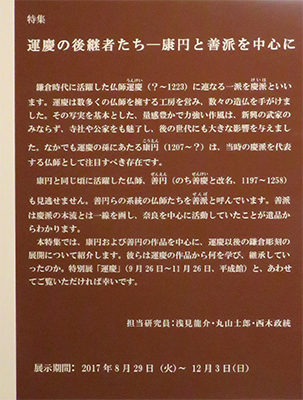 読みづらいので書き起こします。
特集
鎌倉時代に活躍した仏師運慶(?〜1223)に連なる一派を慶派といいます。
運慶は数多くの仏師を擁する工房を営み、数々の造仏を手がけました。
その写実を基本とした、量感豊かで力強い作風は、新興の武家のみならず、
寺社や公家をも魅了し、後の世代にも大きな影響を与えました。
なかでも運慶の孫にあたる康円(こうえん)(1207〜?)は、当時の慶派
を代表する仏師として注目すべき存在です。
康円と同じ頃に活躍した仏師、善円(ぜんえん)(のち善慶と改名、1197
〜1258)も見逃せません。善円らの系統の仏師たちを善派と呼んでいます。
善派は慶派の本流とは一線を画し、奈良を中心に活動していたことが遺品
からわかります。
本特集では、康円および善円の作品を中心に、運慶以後の鎌倉彫刻の展開
について紹介します。彼らは運慶の作品から何を学び、継承していったのか。
特別展「運慶」(9月28日〜11月26日、平成館)と、あわせてご覧いただけ
れば幸いです。
◈◈作品リスト(公式サイトより)
文殊菩薩立像 鎌倉時代・13世紀 C-23
重文 愛染明王坐像 康円作 鎌倉時代・文永12年(1275)京都・神護寺蔵
重文 東方天眷属立像(四天王眷属のうち)
康円作 鎌倉時代・文永4年(1267) C-1834-1
重文 南方天眷属立像(四天王眷属のうち)
康円作 鎌倉時代・文永4年(1267) C-1834-2
重文 地蔵菩薩立像 善円作 鎌倉時代・延応2年(1240)奈良・薬師寺蔵
地蔵菩薩立像 鎌倉時代・13世紀 C-332
重文 菩薩立像 鎌倉時代・13世紀 C-20
重文 文殊菩薩坐像(文殊菩薩騎獅像および侍者立像のうち) 興福寺伝来
康円作 鎌倉時代・文永10年(1273) C-1854-1
重文 獅子像(文殊菩薩騎獅像および侍者立像のうち) 興福寺伝来
康円作 鎌倉時代・文永10年(1273) C-1854-6
重文 光背および蓮華座(文殊菩薩騎獅像および侍者立像のうち)興福寺伝来
康円作 鎌倉時代・文永10年(1273) C-1854-7
重文 仏陀波利三蔵立像(文殊菩薩騎獅像および侍者立像のうち)興福寺伝来
康円作 鎌倉時代・文永10年(1273) C-1854-5
重文 善財童子立像(文殊菩薩騎獅像および侍者立像のうち) 興福寺伝来
康円作 鎌倉時代・文永10年(1273) C-1854-3
重文 ★于てん王立像(文殊菩薩騎獅像および侍者立像のうち) 興福寺伝来
康円作 鎌倉時代・文永10年(1273) C-1854-2
重文 大聖老人立像(文殊菩薩騎獅像および侍者立像のうち) 興福寺伝来
康円作 鎌倉時代・文永10年(1273)) C-1854-4
★てん=門がまえに眞
フラッシュ禁止、撮影可(ないものは撮影不可)でした。
文殊菩薩立像
読みづらいので書き起こします。
特集
鎌倉時代に活躍した仏師運慶(?〜1223)に連なる一派を慶派といいます。
運慶は数多くの仏師を擁する工房を営み、数々の造仏を手がけました。
その写実を基本とした、量感豊かで力強い作風は、新興の武家のみならず、
寺社や公家をも魅了し、後の世代にも大きな影響を与えました。
なかでも運慶の孫にあたる康円(こうえん)(1207〜?)は、当時の慶派
を代表する仏師として注目すべき存在です。
康円と同じ頃に活躍した仏師、善円(ぜんえん)(のち善慶と改名、1197
〜1258)も見逃せません。善円らの系統の仏師たちを善派と呼んでいます。
善派は慶派の本流とは一線を画し、奈良を中心に活動していたことが遺品
からわかります。
本特集では、康円および善円の作品を中心に、運慶以後の鎌倉彫刻の展開
について紹介します。彼らは運慶の作品から何を学び、継承していったのか。
特別展「運慶」(9月28日〜11月26日、平成館)と、あわせてご覧いただけ
れば幸いです。
◈◈作品リスト(公式サイトより)
文殊菩薩立像 鎌倉時代・13世紀 C-23
重文 愛染明王坐像 康円作 鎌倉時代・文永12年(1275)京都・神護寺蔵
重文 東方天眷属立像(四天王眷属のうち)
康円作 鎌倉時代・文永4年(1267) C-1834-1
重文 南方天眷属立像(四天王眷属のうち)
康円作 鎌倉時代・文永4年(1267) C-1834-2
重文 地蔵菩薩立像 善円作 鎌倉時代・延応2年(1240)奈良・薬師寺蔵
地蔵菩薩立像 鎌倉時代・13世紀 C-332
重文 菩薩立像 鎌倉時代・13世紀 C-20
重文 文殊菩薩坐像(文殊菩薩騎獅像および侍者立像のうち) 興福寺伝来
康円作 鎌倉時代・文永10年(1273) C-1854-1
重文 獅子像(文殊菩薩騎獅像および侍者立像のうち) 興福寺伝来
康円作 鎌倉時代・文永10年(1273) C-1854-6
重文 光背および蓮華座(文殊菩薩騎獅像および侍者立像のうち)興福寺伝来
康円作 鎌倉時代・文永10年(1273) C-1854-7
重文 仏陀波利三蔵立像(文殊菩薩騎獅像および侍者立像のうち)興福寺伝来
康円作 鎌倉時代・文永10年(1273) C-1854-5
重文 善財童子立像(文殊菩薩騎獅像および侍者立像のうち) 興福寺伝来
康円作 鎌倉時代・文永10年(1273) C-1854-3
重文 ★于てん王立像(文殊菩薩騎獅像および侍者立像のうち) 興福寺伝来
康円作 鎌倉時代・文永10年(1273) C-1854-2
重文 大聖老人立像(文殊菩薩騎獅像および侍者立像のうち) 興福寺伝来
康円作 鎌倉時代・文永10年(1273)) C-1854-4
★てん=門がまえに眞
フラッシュ禁止、撮影可(ないものは撮影不可)でした。
文殊菩薩立像
 東方天眷属立像、南方天眷属立像
東方天眷属立像、南方天眷属立像
 菩薩立像
菩薩立像

 文殊菩薩坐像
文殊菩薩坐像
 光背および蓮華座
光背および蓮華座
 獅子像
獅子像

 仏陀波利三蔵立像
仏陀波利三蔵立像
 善財童子立像
善財童子立像
 于てん王立像
于てん王立像
 大聖老人立像
大聖老人立像
 唯一善円作の地蔵菩薩、康円の愛染明王は撮影禁止でした…
↑検索してみましたが、慶派の影響を全く受けず、平安時代の作風そのままと
いう感じです。どちらがいいというより、好みですね。
愛染明王は最晩年の作らしく、見た途端に引きつけられる程、細部まで見事な
出来映えでした。頭の獅子?が可愛い(笑)
菩薩立像は作風が定慶風で綺麗ですが、ひねりが入っています。
康円の文殊菩薩は快慶のイメージとは全然違い、何だかしかめ面に見えました。
運慶は仏像を人間に近づけたけど、康円はほぼ人間みたいな距離感(親しみが
持てるという意味)です。
蓮華座の迦陵頻迦(かりょうびんが)は、片方が後補だそうです。
↓向かって左がオリジナル?(違ったりして(笑))
唯一善円作の地蔵菩薩、康円の愛染明王は撮影禁止でした…
↑検索してみましたが、慶派の影響を全く受けず、平安時代の作風そのままと
いう感じです。どちらがいいというより、好みですね。
愛染明王は最晩年の作らしく、見た途端に引きつけられる程、細部まで見事な
出来映えでした。頭の獅子?が可愛い(笑)
菩薩立像は作風が定慶風で綺麗ですが、ひねりが入っています。
康円の文殊菩薩は快慶のイメージとは全然違い、何だかしかめ面に見えました。
運慶は仏像を人間に近づけたけど、康円はほぼ人間みたいな距離感(親しみが
持てるという意味)です。
蓮華座の迦陵頻迦(かりょうびんが)は、片方が後補だそうです。
↓向かって左がオリジナル?(違ったりして(笑))
 康円の特徴はズバリ、目力ならぬへの字眉力とひねりなしの直立(笑)
ちょっと粗い彫りで硬い印象だったけど、愛染明王は素晴らしかったです。
運慶が見たら何と言ったかな…などと思いながら、会場を後にしました。
康円の特徴はズバリ、目力ならぬへの字眉力とひねりなしの直立(笑)
ちょっと粗い彫りで硬い印象だったけど、愛染明王は素晴らしかったです。
運慶が見たら何と言ったかな…などと思いながら、会場を後にしました。