|2011-09-25|空海と密教美術展|東京国立博物館・平成館|
パンフ
 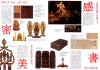  チケット
チケット
 平成館
平成館

 出品目録(P1-4)
出品目録(P1-4)
    会場内の展示は、目録P4をを参考にして下さい。
中央階段を上った所が休憩所、反対側がミュージアムショップです。
仏像が目当てなので、偏った感想になっています(苦笑)
➢➢➢➢第1章・空海-日本密教の祖
書はよくわからない上に、物凄い混雑で近寄るのが大変で、間から何とか見るという状態…
20代の頃の『聾瞽指帰(ろうこしいき)』は、素人目にも迫力のある美しい文字で、若さと
自信に溢れている、そんな力強い書でした。
長すぎて(5m強位?)中心部がたわんだのか、あえてそのまま展示してありました。
和紙の為か状態も良く、墨の色も鮮やかで、直筆の凄みがよく伝わってきました。
『真言七祖像(しんごんしちそぞう)』は、空海の師・恵果他の肖像画で、剥落が酷く、
殆ど何が描かれてあるのかわからないモザイク状態……
『海賦蒔絵袈裟箱(かいぶまきえのけさばこ)』。波と鳥、海獣の文様=海賦だそうです。
現代でも通用しそうな、お洒落なデザインでした。
➢➢➢➢第2章・入唐求法-密教受法と唐文化の吸収
いきなり『兜跋毘沙門天立像(とばつびしゃもんてんりつぞう)』が…
地天女とセットの仏像は初めて見ましたが、図録によると、唐の作品だそうです。
日本のものではない… 表情や頭身、体型が全然違います。
法具は金色に輝き、特に持ち手が黒く摩耗していて、実際に使われた形跡がありました。
錫杖は装飾部分の仏像が3cm位で、荒削りな彫刻という感じです。
仏像画も数点ありましたが、どことなくインド風で、エキゾチックな画風…ですが、『阿修
羅展』で見た法隆寺の厨子と比較すると、日本風にアレンジされている気がしました。
剥落が激しく、目をこらしても「この辺りが顔かな」程度しか判別出来ず、湿度の高い日本
では、幅1m越の大作は保存が相当難しいのかと思いました。
『諸尊仏龕(しょそんぶつがん)』。三面に開ける厨子+仏像です。
表情がインド風で、細部まで丁寧に彫られている見事なものでした。
横から背面が見えましたが、外側はツルツルでした(笑)
➢➢➢➢第3章・密教胎動-神護寺・高野山・東寺
『血曼荼羅』=平清盛の血が使われている為、こう呼ばれる曼荼羅です。
カラフルで、完成当時はさぞかし…と思わせるような細かさ、緻密さでした。
剥落が酷く、展示して大丈夫なのかと不安になりました。
(遺髪が見つかったとか)
仁和寺(にんなじ)の『阿弥陀三尊』はキラキラと輝き、遠くから見た時と、間近で見た時
の印象が全然違いました。顔が丸く、童顔と思える作風は、平安時代の仏像の特徴なのか…
醍醐寺の『如意輪(にょいりん)観音菩薩座像』は、小さめながらも「ふふふ…」という
ような妖しい笑みを浮かべ、やはりどことなくインド風な雰囲気でした。
香川県の聖通寺(しょうつうじ)の『千手観音菩薩立像』。
正面から少し離れて眺めるお顔の、穏やかで素晴らしい事!
平安時代の仏像は…などと思っていたのですが、これはいい!ですね。
じっくり拝観してきました。こういう予期せぬ仏像との出会いは、企画展ならではです。
(図録ではややぽっちゃりで、実物と印象が全然違います)
醍醐寺の『五大明王像』は、揃って展示されていましたが、残念ながら髪の毛がただの板
(暴言)等、立体感や質感が荒削り過ぎて、個人的にはちょっと…(苦笑)
…で、いよいよ東寺の立体曼荼羅(空海はこれを見ていないそうです)のコーナーへ。
➢➢➢➢第4章・法灯-受け継がれる空海の息吹
NHK・BSプレミアム『空海と当時の至宝 第1集』より
左下から右上、対角線上に手すりがあり、少し高い位置から見下ろせ、右奥で左下に降ります。
会場内の展示は、目録P4をを参考にして下さい。
中央階段を上った所が休憩所、反対側がミュージアムショップです。
仏像が目当てなので、偏った感想になっています(苦笑)
➢➢➢➢第1章・空海-日本密教の祖
書はよくわからない上に、物凄い混雑で近寄るのが大変で、間から何とか見るという状態…
20代の頃の『聾瞽指帰(ろうこしいき)』は、素人目にも迫力のある美しい文字で、若さと
自信に溢れている、そんな力強い書でした。
長すぎて(5m強位?)中心部がたわんだのか、あえてそのまま展示してありました。
和紙の為か状態も良く、墨の色も鮮やかで、直筆の凄みがよく伝わってきました。
『真言七祖像(しんごんしちそぞう)』は、空海の師・恵果他の肖像画で、剥落が酷く、
殆ど何が描かれてあるのかわからないモザイク状態……
『海賦蒔絵袈裟箱(かいぶまきえのけさばこ)』。波と鳥、海獣の文様=海賦だそうです。
現代でも通用しそうな、お洒落なデザインでした。
➢➢➢➢第2章・入唐求法-密教受法と唐文化の吸収
いきなり『兜跋毘沙門天立像(とばつびしゃもんてんりつぞう)』が…
地天女とセットの仏像は初めて見ましたが、図録によると、唐の作品だそうです。
日本のものではない… 表情や頭身、体型が全然違います。
法具は金色に輝き、特に持ち手が黒く摩耗していて、実際に使われた形跡がありました。
錫杖は装飾部分の仏像が3cm位で、荒削りな彫刻という感じです。
仏像画も数点ありましたが、どことなくインド風で、エキゾチックな画風…ですが、『阿修
羅展』で見た法隆寺の厨子と比較すると、日本風にアレンジされている気がしました。
剥落が激しく、目をこらしても「この辺りが顔かな」程度しか判別出来ず、湿度の高い日本
では、幅1m越の大作は保存が相当難しいのかと思いました。
『諸尊仏龕(しょそんぶつがん)』。三面に開ける厨子+仏像です。
表情がインド風で、細部まで丁寧に彫られている見事なものでした。
横から背面が見えましたが、外側はツルツルでした(笑)
➢➢➢➢第3章・密教胎動-神護寺・高野山・東寺
『血曼荼羅』=平清盛の血が使われている為、こう呼ばれる曼荼羅です。
カラフルで、完成当時はさぞかし…と思わせるような細かさ、緻密さでした。
剥落が酷く、展示して大丈夫なのかと不安になりました。
(遺髪が見つかったとか)
仁和寺(にんなじ)の『阿弥陀三尊』はキラキラと輝き、遠くから見た時と、間近で見た時
の印象が全然違いました。顔が丸く、童顔と思える作風は、平安時代の仏像の特徴なのか…
醍醐寺の『如意輪(にょいりん)観音菩薩座像』は、小さめながらも「ふふふ…」という
ような妖しい笑みを浮かべ、やはりどことなくインド風な雰囲気でした。
香川県の聖通寺(しょうつうじ)の『千手観音菩薩立像』。
正面から少し離れて眺めるお顔の、穏やかで素晴らしい事!
平安時代の仏像は…などと思っていたのですが、これはいい!ですね。
じっくり拝観してきました。こういう予期せぬ仏像との出会いは、企画展ならではです。
(図録ではややぽっちゃりで、実物と印象が全然違います)
醍醐寺の『五大明王像』は、揃って展示されていましたが、残念ながら髪の毛がただの板
(暴言)等、立体感や質感が荒削り過ぎて、個人的にはちょっと…(苦笑)
…で、いよいよ東寺の立体曼荼羅(空海はこれを見ていないそうです)のコーナーへ。
➢➢➢➢第4章・法灯-受け継がれる空海の息吹
NHK・BSプレミアム『空海と当時の至宝 第1集』より
左下から右上、対角線上に手すりがあり、少し高い位置から見下ろせ、右奥で左下に降ります。
 台座は円形です。
台座は円形です。
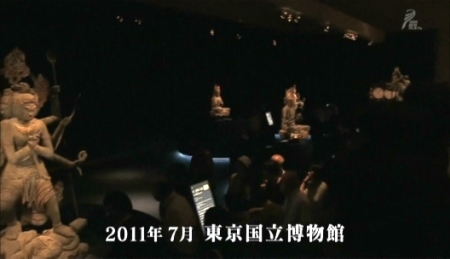
 …書の混雑ぶりが何だったのかと思う位、比較的空いていたのが意外でした。
……でも暑い…………
『梵天(ぼんてん)座像』。如意輪観音と同じような妖しさを漂わせています。
なだらかというよりムチムチ(笑)
『持国天(じこくてん)立像』。丸味を帯び、いかにも重たそうなずっしりとした作風です。
持国天は「カァッ!」と怒りの表情なのに、踏みつけられている悪鬼は可愛らしい(笑)
『金剛法(こんごうほう)菩薩座像』と『金剛業(こんごうごう)菩薩座像』。
運慶の大日如来に何となく似ている面差し、双子のようにそっくりな二躰ですが、左手のポーズ
が違います。少し微笑んでいるように見えました。
『降三世明王立像(こうざんぜみょうおうりつぞう)』。右足で女性、左足で男性を踏みつけ
ていて、説明文で「なぜ自分の奥さんを?…」と勘違い(笑)
降三世明王=シヴァ神を降ろすという意味で、男性はヒンドゥー教の有力神、女性はその妻です。
全体的に丸いせいか、悲惨さ、酷さは感じられませんでした。
『大威德明王騎牛像(だいいとくみょうおうきぎゅうぞう)』。水牛はヒンドゥー教の死の神
ヤマで、それに乗る=調伏だそうです。
むっちりした腕と足、睨んでいるとあるのにうなだれて見える水牛。
迫力はあるけど恐くはない… 角度かと思い、下から見上げてみましたが、印象は同じでした。
『増長天(ぞうちょうてん)立像』。日本で一番怖い表情だそうです。
さっきの毘沙門天とは全く共通点がない(笑)鎧の細かい表現、大きな目、投げやりな悪鬼(笑)
背面を見られる機会は滅多にないので、構造をじっくり眺めて来ました。
『帝釈天騎象像(たいしゃくてんきぞうぞう)』。顔は後で造り直されたものだそうです。
恐らく、東寺&日本の帝釈天の中で一番人気の仏像です。グッズも色々ありました(笑)
しっぽや重みで出来る皺、ニッコリ笑っているような表情と、象がとても可愛らしい…
耳は束ねているのか…などと考えていたら、「御飯3杯いけるよね~」の声が(リアルで初めて
聞いた(笑))
独特な髪の結い方、画像では右斜めからの構図が殆どなので、初めて正面のお顔を見る事が
出来ました。…このアングルが一番いいと思うのですが、なぜか図録にもグッズにもなし。
➢➢この後ミュージアム・ショップへ。
物凄い程ではないけど、やや混雑してました。左手に絵葉書とクリアファイル、東寺の仏像の
グッズ、金平糖などのお菓子、中央には東寺フィギュア6点(売り切れはなし)他、中央奥は
筆など書関連、右手は東博グッズ。
ここが一番気温が高かったのは、白熱灯クリア(裸電球)の光が、商品の金属で乱反射して
いた、東博スペースのせいかと…(LED導入して下さい)
象が可愛い帝釈天フィギュア(小さい。高さ約11㎝)等、目的の品を無事購入。
図録はソフトカバーで軽くなっていたのですが、仏像の画像が殆ど正面と全身だけと、少な
すぎてガッカリ。資料にしたかったのに……(書と曼荼羅、仏像の2冊に分けて欲しかった)
混雑しているのに、相変わらずへばりついて動かない人の多かった事……
09-02・入館者数20万人突破、09-13・40万人突破、09-22・50万人突破と、物凄い勢いで、
私もですが、7-8月の猛暑時は避けたのかもしれません。(日傘の貸出をしていましたが、
ふくらはぎが焦げるかと思う程、アスファルトの反射熱の方が凄かったです)
仏像のコーナーが空いていて、じっくり見られたのが救いですが、展示品保護と節電とはいえ、
空調が効いていないのには参りました。(真夏はキツイ……)
書や仏具、曼荼羅や立体曼荼羅… 生きていた証が、教えが今も残る空海。
唐の毘沙門天と日本の仏像とは全然違うので、インドの影響がそのまま日本に伝わり、アレ
ンジされたと思いました。
BSの特番(仏像の時間が少なくて残念。30分のドラマの為なら尚更)によると、曼荼羅に
描かれているポーズはインド舞踊とよく似ているそうです。
緻密で美しく、派手でエキゾチック。密教ならではの色遣いや造形が、日本でワビサビの仏教
と同居しているのは、何だか不思議でした。
➢➢おまけです。
平成館(左)と本館の間から、スカイツリーの上部が見えました。
映像で見慣れた風景ですが、実物は遠目でも迫力がありました。
…書の混雑ぶりが何だったのかと思う位、比較的空いていたのが意外でした。
……でも暑い…………
『梵天(ぼんてん)座像』。如意輪観音と同じような妖しさを漂わせています。
なだらかというよりムチムチ(笑)
『持国天(じこくてん)立像』。丸味を帯び、いかにも重たそうなずっしりとした作風です。
持国天は「カァッ!」と怒りの表情なのに、踏みつけられている悪鬼は可愛らしい(笑)
『金剛法(こんごうほう)菩薩座像』と『金剛業(こんごうごう)菩薩座像』。
運慶の大日如来に何となく似ている面差し、双子のようにそっくりな二躰ですが、左手のポーズ
が違います。少し微笑んでいるように見えました。
『降三世明王立像(こうざんぜみょうおうりつぞう)』。右足で女性、左足で男性を踏みつけ
ていて、説明文で「なぜ自分の奥さんを?…」と勘違い(笑)
降三世明王=シヴァ神を降ろすという意味で、男性はヒンドゥー教の有力神、女性はその妻です。
全体的に丸いせいか、悲惨さ、酷さは感じられませんでした。
『大威德明王騎牛像(だいいとくみょうおうきぎゅうぞう)』。水牛はヒンドゥー教の死の神
ヤマで、それに乗る=調伏だそうです。
むっちりした腕と足、睨んでいるとあるのにうなだれて見える水牛。
迫力はあるけど恐くはない… 角度かと思い、下から見上げてみましたが、印象は同じでした。
『増長天(ぞうちょうてん)立像』。日本で一番怖い表情だそうです。
さっきの毘沙門天とは全く共通点がない(笑)鎧の細かい表現、大きな目、投げやりな悪鬼(笑)
背面を見られる機会は滅多にないので、構造をじっくり眺めて来ました。
『帝釈天騎象像(たいしゃくてんきぞうぞう)』。顔は後で造り直されたものだそうです。
恐らく、東寺&日本の帝釈天の中で一番人気の仏像です。グッズも色々ありました(笑)
しっぽや重みで出来る皺、ニッコリ笑っているような表情と、象がとても可愛らしい…
耳は束ねているのか…などと考えていたら、「御飯3杯いけるよね~」の声が(リアルで初めて
聞いた(笑))
独特な髪の結い方、画像では右斜めからの構図が殆どなので、初めて正面のお顔を見る事が
出来ました。…このアングルが一番いいと思うのですが、なぜか図録にもグッズにもなし。
➢➢この後ミュージアム・ショップへ。
物凄い程ではないけど、やや混雑してました。左手に絵葉書とクリアファイル、東寺の仏像の
グッズ、金平糖などのお菓子、中央には東寺フィギュア6点(売り切れはなし)他、中央奥は
筆など書関連、右手は東博グッズ。
ここが一番気温が高かったのは、白熱灯クリア(裸電球)の光が、商品の金属で乱反射して
いた、東博スペースのせいかと…(LED導入して下さい)
象が可愛い帝釈天フィギュア(小さい。高さ約11㎝)等、目的の品を無事購入。
図録はソフトカバーで軽くなっていたのですが、仏像の画像が殆ど正面と全身だけと、少な
すぎてガッカリ。資料にしたかったのに……(書と曼荼羅、仏像の2冊に分けて欲しかった)
混雑しているのに、相変わらずへばりついて動かない人の多かった事……
09-02・入館者数20万人突破、09-13・40万人突破、09-22・50万人突破と、物凄い勢いで、
私もですが、7-8月の猛暑時は避けたのかもしれません。(日傘の貸出をしていましたが、
ふくらはぎが焦げるかと思う程、アスファルトの反射熱の方が凄かったです)
仏像のコーナーが空いていて、じっくり見られたのが救いですが、展示品保護と節電とはいえ、
空調が効いていないのには参りました。(真夏はキツイ……)
書や仏具、曼荼羅や立体曼荼羅… 生きていた証が、教えが今も残る空海。
唐の毘沙門天と日本の仏像とは全然違うので、インドの影響がそのまま日本に伝わり、アレ
ンジされたと思いました。
BSの特番(仏像の時間が少なくて残念。30分のドラマの為なら尚更)によると、曼荼羅に
描かれているポーズはインド舞踊とよく似ているそうです。
緻密で美しく、派手でエキゾチック。密教ならではの色遣いや造形が、日本でワビサビの仏教
と同居しているのは、何だか不思議でした。
➢➢おまけです。
平成館(左)と本館の間から、スカイツリーの上部が見えました。
映像で見慣れた風景ですが、実物は遠目でも迫力がありました。

 …この後、本館14室の『運慶とその周辺の仏像』へ行きました。
宜しければこちらもお読み下さい。
…この後、本館14室の『運慶とその周辺の仏像』へ行きました。
宜しければこちらもお読み下さい。
|

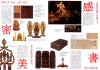
 チケット
チケット
 平成館
平成館

 出品目録(P1-4)
出品目録(P1-4)



 会場内の展示は、目録P4をを参考にして下さい。
中央階段を上った所が休憩所、反対側がミュージアムショップです。
仏像が目当てなので、偏った感想になっています(苦笑)
➢➢➢➢第1章・空海-日本密教の祖
書はよくわからない上に、物凄い混雑で近寄るのが大変で、間から何とか見るという状態…
20代の頃の『聾瞽指帰(ろうこしいき)』は、素人目にも迫力のある美しい文字で、若さと
自信に溢れている、そんな力強い書でした。
長すぎて(5m強位?)中心部がたわんだのか、あえてそのまま展示してありました。
和紙の為か状態も良く、墨の色も鮮やかで、直筆の凄みがよく伝わってきました。
『真言七祖像(しんごんしちそぞう)』は、空海の師・恵果他の肖像画で、剥落が酷く、
殆ど何が描かれてあるのかわからないモザイク状態……
『海賦蒔絵袈裟箱(かいぶまきえのけさばこ)』。波と鳥、海獣の文様=海賦だそうです。
現代でも通用しそうな、お洒落なデザインでした。
➢➢➢➢第2章・入唐求法-密教受法と唐文化の吸収
いきなり『兜跋毘沙門天立像(とばつびしゃもんてんりつぞう)』が…
地天女とセットの仏像は初めて見ましたが、図録によると、唐の作品だそうです。
日本のものではない… 表情や頭身、体型が全然違います。
法具は金色に輝き、特に持ち手が黒く摩耗していて、実際に使われた形跡がありました。
錫杖は装飾部分の仏像が3cm位で、荒削りな彫刻という感じです。
仏像画も数点ありましたが、どことなくインド風で、エキゾチックな画風…ですが、『阿修
羅展』で見た法隆寺の厨子と比較すると、日本風にアレンジされている気がしました。
剥落が激しく、目をこらしても「この辺りが顔かな」程度しか判別出来ず、湿度の高い日本
では、幅1m越の大作は保存が相当難しいのかと思いました。
『諸尊仏龕(しょそんぶつがん)』。三面に開ける厨子+仏像です。
表情がインド風で、細部まで丁寧に彫られている見事なものでした。
横から背面が見えましたが、外側はツルツルでした(笑)
➢➢➢➢第3章・密教胎動-神護寺・高野山・東寺
『血曼荼羅』=平清盛の血が使われている為、こう呼ばれる曼荼羅です。
カラフルで、完成当時はさぞかし…と思わせるような細かさ、緻密さでした。
剥落が酷く、展示して大丈夫なのかと不安になりました。
(遺髪が見つかったとか)
仁和寺(にんなじ)の『阿弥陀三尊』はキラキラと輝き、遠くから見た時と、間近で見た時
の印象が全然違いました。顔が丸く、童顔と思える作風は、平安時代の仏像の特徴なのか…
醍醐寺の『如意輪(にょいりん)観音菩薩座像』は、小さめながらも「ふふふ…」という
ような妖しい笑みを浮かべ、やはりどことなくインド風な雰囲気でした。
香川県の聖通寺(しょうつうじ)の『千手観音菩薩立像』。
正面から少し離れて眺めるお顔の、穏やかで素晴らしい事!
平安時代の仏像は…などと思っていたのですが、これはいい!ですね。
じっくり拝観してきました。こういう予期せぬ仏像との出会いは、企画展ならではです。
(図録ではややぽっちゃりで、実物と印象が全然違います)
醍醐寺の『五大明王像』は、揃って展示されていましたが、残念ながら髪の毛がただの板
(暴言)等、立体感や質感が荒削り過ぎて、個人的にはちょっと…(苦笑)
…で、いよいよ東寺の立体曼荼羅(空海はこれを見ていないそうです)のコーナーへ。
➢➢➢➢第4章・法灯-受け継がれる空海の息吹
NHK・BSプレミアム『空海と当時の至宝 第1集』より
左下から右上、対角線上に手すりがあり、少し高い位置から見下ろせ、右奥で左下に降ります。
会場内の展示は、目録P4をを参考にして下さい。
中央階段を上った所が休憩所、反対側がミュージアムショップです。
仏像が目当てなので、偏った感想になっています(苦笑)
➢➢➢➢第1章・空海-日本密教の祖
書はよくわからない上に、物凄い混雑で近寄るのが大変で、間から何とか見るという状態…
20代の頃の『聾瞽指帰(ろうこしいき)』は、素人目にも迫力のある美しい文字で、若さと
自信に溢れている、そんな力強い書でした。
長すぎて(5m強位?)中心部がたわんだのか、あえてそのまま展示してありました。
和紙の為か状態も良く、墨の色も鮮やかで、直筆の凄みがよく伝わってきました。
『真言七祖像(しんごんしちそぞう)』は、空海の師・恵果他の肖像画で、剥落が酷く、
殆ど何が描かれてあるのかわからないモザイク状態……
『海賦蒔絵袈裟箱(かいぶまきえのけさばこ)』。波と鳥、海獣の文様=海賦だそうです。
現代でも通用しそうな、お洒落なデザインでした。
➢➢➢➢第2章・入唐求法-密教受法と唐文化の吸収
いきなり『兜跋毘沙門天立像(とばつびしゃもんてんりつぞう)』が…
地天女とセットの仏像は初めて見ましたが、図録によると、唐の作品だそうです。
日本のものではない… 表情や頭身、体型が全然違います。
法具は金色に輝き、特に持ち手が黒く摩耗していて、実際に使われた形跡がありました。
錫杖は装飾部分の仏像が3cm位で、荒削りな彫刻という感じです。
仏像画も数点ありましたが、どことなくインド風で、エキゾチックな画風…ですが、『阿修
羅展』で見た法隆寺の厨子と比較すると、日本風にアレンジされている気がしました。
剥落が激しく、目をこらしても「この辺りが顔かな」程度しか判別出来ず、湿度の高い日本
では、幅1m越の大作は保存が相当難しいのかと思いました。
『諸尊仏龕(しょそんぶつがん)』。三面に開ける厨子+仏像です。
表情がインド風で、細部まで丁寧に彫られている見事なものでした。
横から背面が見えましたが、外側はツルツルでした(笑)
➢➢➢➢第3章・密教胎動-神護寺・高野山・東寺
『血曼荼羅』=平清盛の血が使われている為、こう呼ばれる曼荼羅です。
カラフルで、完成当時はさぞかし…と思わせるような細かさ、緻密さでした。
剥落が酷く、展示して大丈夫なのかと不安になりました。
(遺髪が見つかったとか)
仁和寺(にんなじ)の『阿弥陀三尊』はキラキラと輝き、遠くから見た時と、間近で見た時
の印象が全然違いました。顔が丸く、童顔と思える作風は、平安時代の仏像の特徴なのか…
醍醐寺の『如意輪(にょいりん)観音菩薩座像』は、小さめながらも「ふふふ…」という
ような妖しい笑みを浮かべ、やはりどことなくインド風な雰囲気でした。
香川県の聖通寺(しょうつうじ)の『千手観音菩薩立像』。
正面から少し離れて眺めるお顔の、穏やかで素晴らしい事!
平安時代の仏像は…などと思っていたのですが、これはいい!ですね。
じっくり拝観してきました。こういう予期せぬ仏像との出会いは、企画展ならではです。
(図録ではややぽっちゃりで、実物と印象が全然違います)
醍醐寺の『五大明王像』は、揃って展示されていましたが、残念ながら髪の毛がただの板
(暴言)等、立体感や質感が荒削り過ぎて、個人的にはちょっと…(苦笑)
…で、いよいよ東寺の立体曼荼羅(空海はこれを見ていないそうです)のコーナーへ。
➢➢➢➢第4章・法灯-受け継がれる空海の息吹
NHK・BSプレミアム『空海と当時の至宝 第1集』より
左下から右上、対角線上に手すりがあり、少し高い位置から見下ろせ、右奥で左下に降ります。
 台座は円形です。
台座は円形です。
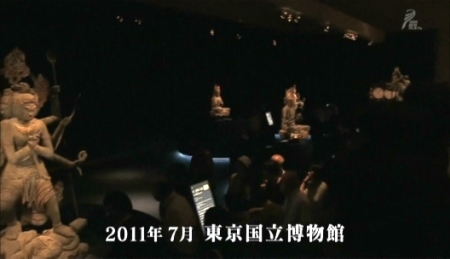
 …書の混雑ぶりが何だったのかと思う位、比較的空いていたのが意外でした。
……でも暑い…………
『梵天(ぼんてん)座像』。如意輪観音と同じような妖しさを漂わせています。
なだらかというよりムチムチ(笑)
『持国天(じこくてん)立像』。丸味を帯び、いかにも重たそうなずっしりとした作風です。
持国天は「カァッ!」と怒りの表情なのに、踏みつけられている悪鬼は可愛らしい(笑)
『金剛法(こんごうほう)菩薩座像』と『金剛業(こんごうごう)菩薩座像』。
運慶の大日如来に何となく似ている面差し、双子のようにそっくりな二躰ですが、左手のポーズ
が違います。少し微笑んでいるように見えました。
『降三世明王立像(こうざんぜみょうおうりつぞう)』。右足で女性、左足で男性を踏みつけ
ていて、説明文で「なぜ自分の奥さんを?…」と勘違い(笑)
降三世明王=シヴァ神を降ろすという意味で、男性はヒンドゥー教の有力神、女性はその妻です。
全体的に丸いせいか、悲惨さ、酷さは感じられませんでした。
『大威德明王騎牛像(だいいとくみょうおうきぎゅうぞう)』。水牛はヒンドゥー教の死の神
ヤマで、それに乗る=調伏だそうです。
むっちりした腕と足、睨んでいるとあるのにうなだれて見える水牛。
迫力はあるけど恐くはない… 角度かと思い、下から見上げてみましたが、印象は同じでした。
『増長天(ぞうちょうてん)立像』。日本で一番怖い表情だそうです。
さっきの毘沙門天とは全く共通点がない(笑)鎧の細かい表現、大きな目、投げやりな悪鬼(笑)
背面を見られる機会は滅多にないので、構造をじっくり眺めて来ました。
『帝釈天騎象像(たいしゃくてんきぞうぞう)』。顔は後で造り直されたものだそうです。
恐らく、東寺&日本の帝釈天の中で一番人気の仏像です。グッズも色々ありました(笑)
しっぽや重みで出来る皺、ニッコリ笑っているような表情と、象がとても可愛らしい…
耳は束ねているのか…などと考えていたら、「御飯3杯いけるよね~」の声が(リアルで初めて
聞いた(笑))
独特な髪の結い方、画像では右斜めからの構図が殆どなので、初めて正面のお顔を見る事が
出来ました。…このアングルが一番いいと思うのですが、なぜか図録にもグッズにもなし。
➢➢この後ミュージアム・ショップへ。
物凄い程ではないけど、やや混雑してました。左手に絵葉書とクリアファイル、東寺の仏像の
グッズ、金平糖などのお菓子、中央には東寺フィギュア6点(売り切れはなし)他、中央奥は
筆など書関連、右手は東博グッズ。
ここが一番気温が高かったのは、白熱灯クリア(裸電球)の光が、商品の金属で乱反射して
いた、東博スペースのせいかと…(LED導入して下さい)
象が可愛い帝釈天フィギュア(小さい。高さ約11㎝)等、目的の品を無事購入。
図録はソフトカバーで軽くなっていたのですが、仏像の画像が殆ど正面と全身だけと、少な
すぎてガッカリ。資料にしたかったのに……(書と曼荼羅、仏像の2冊に分けて欲しかった)
混雑しているのに、相変わらずへばりついて動かない人の多かった事……
09-02・入館者数20万人突破、09-13・40万人突破、09-22・50万人突破と、物凄い勢いで、
私もですが、7-8月の猛暑時は避けたのかもしれません。(日傘の貸出をしていましたが、
ふくらはぎが焦げるかと思う程、アスファルトの反射熱の方が凄かったです)
仏像のコーナーが空いていて、じっくり見られたのが救いですが、展示品保護と節電とはいえ、
空調が効いていないのには参りました。(真夏はキツイ……)
書や仏具、曼荼羅や立体曼荼羅… 生きていた証が、教えが今も残る空海。
唐の毘沙門天と日本の仏像とは全然違うので、インドの影響がそのまま日本に伝わり、アレ
ンジされたと思いました。
BSの特番(仏像の時間が少なくて残念。30分のドラマの為なら尚更)によると、曼荼羅に
描かれているポーズはインド舞踊とよく似ているそうです。
緻密で美しく、派手でエキゾチック。密教ならではの色遣いや造形が、日本でワビサビの仏教
と同居しているのは、何だか不思議でした。
➢➢おまけです。
平成館(左)と本館の間から、スカイツリーの上部が見えました。
映像で見慣れた風景ですが、実物は遠目でも迫力がありました。
…書の混雑ぶりが何だったのかと思う位、比較的空いていたのが意外でした。
……でも暑い…………
『梵天(ぼんてん)座像』。如意輪観音と同じような妖しさを漂わせています。
なだらかというよりムチムチ(笑)
『持国天(じこくてん)立像』。丸味を帯び、いかにも重たそうなずっしりとした作風です。
持国天は「カァッ!」と怒りの表情なのに、踏みつけられている悪鬼は可愛らしい(笑)
『金剛法(こんごうほう)菩薩座像』と『金剛業(こんごうごう)菩薩座像』。
運慶の大日如来に何となく似ている面差し、双子のようにそっくりな二躰ですが、左手のポーズ
が違います。少し微笑んでいるように見えました。
『降三世明王立像(こうざんぜみょうおうりつぞう)』。右足で女性、左足で男性を踏みつけ
ていて、説明文で「なぜ自分の奥さんを?…」と勘違い(笑)
降三世明王=シヴァ神を降ろすという意味で、男性はヒンドゥー教の有力神、女性はその妻です。
全体的に丸いせいか、悲惨さ、酷さは感じられませんでした。
『大威德明王騎牛像(だいいとくみょうおうきぎゅうぞう)』。水牛はヒンドゥー教の死の神
ヤマで、それに乗る=調伏だそうです。
むっちりした腕と足、睨んでいるとあるのにうなだれて見える水牛。
迫力はあるけど恐くはない… 角度かと思い、下から見上げてみましたが、印象は同じでした。
『増長天(ぞうちょうてん)立像』。日本で一番怖い表情だそうです。
さっきの毘沙門天とは全く共通点がない(笑)鎧の細かい表現、大きな目、投げやりな悪鬼(笑)
背面を見られる機会は滅多にないので、構造をじっくり眺めて来ました。
『帝釈天騎象像(たいしゃくてんきぞうぞう)』。顔は後で造り直されたものだそうです。
恐らく、東寺&日本の帝釈天の中で一番人気の仏像です。グッズも色々ありました(笑)
しっぽや重みで出来る皺、ニッコリ笑っているような表情と、象がとても可愛らしい…
耳は束ねているのか…などと考えていたら、「御飯3杯いけるよね~」の声が(リアルで初めて
聞いた(笑))
独特な髪の結い方、画像では右斜めからの構図が殆どなので、初めて正面のお顔を見る事が
出来ました。…このアングルが一番いいと思うのですが、なぜか図録にもグッズにもなし。
➢➢この後ミュージアム・ショップへ。
物凄い程ではないけど、やや混雑してました。左手に絵葉書とクリアファイル、東寺の仏像の
グッズ、金平糖などのお菓子、中央には東寺フィギュア6点(売り切れはなし)他、中央奥は
筆など書関連、右手は東博グッズ。
ここが一番気温が高かったのは、白熱灯クリア(裸電球)の光が、商品の金属で乱反射して
いた、東博スペースのせいかと…(LED導入して下さい)
象が可愛い帝釈天フィギュア(小さい。高さ約11㎝)等、目的の品を無事購入。
図録はソフトカバーで軽くなっていたのですが、仏像の画像が殆ど正面と全身だけと、少な
すぎてガッカリ。資料にしたかったのに……(書と曼荼羅、仏像の2冊に分けて欲しかった)
混雑しているのに、相変わらずへばりついて動かない人の多かった事……
09-02・入館者数20万人突破、09-13・40万人突破、09-22・50万人突破と、物凄い勢いで、
私もですが、7-8月の猛暑時は避けたのかもしれません。(日傘の貸出をしていましたが、
ふくらはぎが焦げるかと思う程、アスファルトの反射熱の方が凄かったです)
仏像のコーナーが空いていて、じっくり見られたのが救いですが、展示品保護と節電とはいえ、
空調が効いていないのには参りました。(真夏はキツイ……)
書や仏具、曼荼羅や立体曼荼羅… 生きていた証が、教えが今も残る空海。
唐の毘沙門天と日本の仏像とは全然違うので、インドの影響がそのまま日本に伝わり、アレ
ンジされたと思いました。
BSの特番(仏像の時間が少なくて残念。30分のドラマの為なら尚更)によると、曼荼羅に
描かれているポーズはインド舞踊とよく似ているそうです。
緻密で美しく、派手でエキゾチック。密教ならではの色遣いや造形が、日本でワビサビの仏教
と同居しているのは、何だか不思議でした。
➢➢おまけです。
平成館(左)と本館の間から、スカイツリーの上部が見えました。
映像で見慣れた風景ですが、実物は遠目でも迫力がありました。

 …この後、本館14室の『運慶とその周辺の仏像』へ行きました。
宜しければこちらもお読み下さい。
…この後、本館14室の『運慶とその周辺の仏像』へ行きました。
宜しければこちらもお読み下さい。